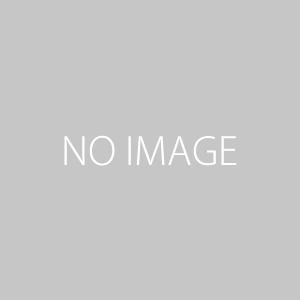志波彦神社・鹽竈神社|東北鎮護の由緒ある神社の歴史と見どころ、参拝情報を完全ガイド
宮城県塩竈市の一森山に鎮座する志波彦神社・鹽竈神社は、1200年以上の歴史を誇る東北地方屈指の名社です。陸奥国一宮として古くから朝廷や庶民の篤い信仰を集め、現在も年間50万人もの参拝者が訪れます。国の天然記念物「鹽竈桜」をはじめ、重要文化財に指定された社殿群や壮大な祭礼など、多彩な魅力を持つ神社の全貌をご紹介します。
志波彦神社・鹽竈神社の概要・基本情報

宮城県塩竈市の市街地を見下ろす一森山の頂上に位置する志波彦神社・鹽竈神社は、正式名称を「志波彦神社・鹽竈神社」とする二社一体の神社です。元は当地には鹽竈神社のみが鎮座していたが、明治時代に志波彦神社が境内に遷座し、現在は正式名称を「志波彦神社・鹽竈神社」とし1つの法人となっているという経緯があります。
鹽竈神社は全国にある鹽竈(鹽竃・塩竈・塩竃・塩釜・塩釡)神社の総本社であるとして知られ、志波彦神社は式内社(名神大社)。鹽竈神社は式外社、陸奥国一宮という格式を誇ります。両社合わせて旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社に指定されています。
境内は約3万平方メートルの広大な敷地を有し、神社の敷地は、塩竈市と松島湾の島々を見晴らす約3万平方メートルの高台です。この立地から、塩竈市街や松島湾の美しい景観を一望することができます。
歴史と由来
鹽竈神社の創建は古く、正確な年代は不明ですが、鹽竈神社は奈良時代(710–794)より前に創建されたと考えられています。神社の起源について、鹽竈神社は、武甕槌命・経津主神が東北を平定した際に両神を先導した塩土老翁神がこの地に留まり、現地の人々に製塩を教えたことに始まると伝えられるとされています。
正史における初見は、弘仁11年(820年)に撰進された『弘仁式』の『主税式』では「鹽竈神を祭る料壹萬束」と記載され、祭祀料10,000束を国家から受けており、これが正史における鹽竈神社の初見と言われていることから、平安時代初期には既に国家的な重要性を持つ神社として認識されていたことが分かります。
一方、志波彦神社は元々は東山道より多賀城に至る交通の要所宮城郡岩切村(現仙台市宮城野区岩切)の冠川の辺(現八坂神社境内)に鎮座しておりましたが、中世以降衰微の一途をたどり、志波彦神社はより近年の1874年に現在の場所に移されましたという歴史があります。
明治時代の遷座について、明治4年の国幣中社列格の際に社殿造営の事が検討され、明治7年12月24日この地を離れ鹽竈神社別宮に遷座され、その後昭和9年に着手、明治・大正・昭和の神社建築の粋を集め昭和13年に完成したのが現社殿ですとなっています。
祭神とご利益
鹽竈神社には三柱の神が祀られています。海の守護神であり人々に製塩の方法を伝授した鹽土老翁神(シオツチノオジノカミ)は別宮に祀られています。戦の神である武甕槌神(タケミカヅチノカミ)と経津主神(フツヌシノカミ)はそれぞれ左宮と右宮に祀られています。
鹽土老翁神は、塩土老翁神は謎の多い神であるが、海や塩の神格化と考えられている。神武天皇や山幸彦を導いたことから、航海安全・交通安全の神徳を持つものとしても見られる。また安産祈願の神でもあるとされ、製塩技術を伝えた神として信仰されています。
志波彦神社には、塩竈地域の守護神でもある農耕の神・志波彦神(シワヒコノカミ)を祀っています。こちらは農耕守護・国土開発・殖産の神として信仰されています。
両神社のご利益として、安産守護・延命長寿・大漁などが挙げられ、特に昔から航海安全・安産の神様として信仰されてきましたということから、海に関わる仕事に従事する人々や妊娠・出産を控えた女性からの信仰が篤くなっています。
志波彦神社・鹽竈神社の見どころ・特徴

志波彦神社・鹽竈神社は、歴史的価値の高い建造物群と美しい自然環境が調和した境内が大きな魅力です。2012年、本殿や拝殿、石鳥居などが国の重要文化財の指定を受けましたことからも、その文化的価値の高さが伺えます。参拝者は両脇に杉の木立が鬱蒼と茂り、石灯籠が立ち並ぶ202段の石段を登って社殿に向かいますという荘厳な参道を通って境内に向かいます。
建造物・構造の魅力
鹽竈神社の本殿は1704年に建立された本殿は、背面より全面が長い非対称の傾斜屋根を持つ流造(ながれづくり)という建築様式で建てられています。この流造は神社建築の代表的な様式の一つで、正面から見ると屋根が流れるような美しい曲線を描いているのが特徴です。
一方、志波彦神社の社殿は鹽竈神社とは対照的な美しさを持ちます。黒と朱で塗られた豪華な本殿は、1938年に建て直されたものです。鹽竈神社とは趣を別にし、本殿・拝殿ともに朱黒漆塗りの極彩色社殿となっておりますという華やかな装飾が施されており、又全額国費を以て造られた最後の神社とも言われておりますという歴史的価値も持っています。
境内への入口となる随神門も見どころの一つです。階段の上にそびえる重厚な随神門(1700年代建造)をくぐると神社の中心部にたどり着きます。この随神門は江戸時代中期の建造で、長い歴史を物語る風格ある佇まいを見せています。
国の天然記念物「鹽竈桜」と境内の自然
志波彦神社・鹽竈神社の最大の自然の見どころは、国の天然記念物に指定されている塩竈桜(シオガマザクラ)があり、毎年当地の報道で取り上げられている鹽竈桜です。この桜は4月下旬頃になるとふんわりとした丸いかたちの薄桃色の花を咲かせますという独特の美しさを持ち、塩竈桜は4月下旬から5月上旬にかけてふわふわした八重の花を咲かせます。
境内の桜はこの鹽竈桜だけではありません。境内には、国指定重要文化財の社殿14棟に加え、落ち着いた日本庭園や40品種約300本の桜の木があります。その他にも、神社の敷地内にはソメイヨシノを始め数十種類もの桜が植えられており、春にはお花見の名所にもなるとのことですということから、多様な桜を楽しむことができます。
春の桜の季節には特別なライトアップも行われ、春には日没後に桜がライトアップされ、昼間とは異なる幻想的な美しさを楽しむことができます。
境内からの眺望も素晴らしく、志波彦神社の門の外あたりから庭園を見下ろすと、その先には塩釜の町と海が見えます。この高台からの景色は四季を通じて美しく、特に春から秋にかけては色とりどりの花や緑で飾られる光景が広がり、よりフォトジェニックになりますとされています。
鹽竈神社博物館と文化財
境内には神社境内には鹽竈神社博物館があり、鹽竈神社にかかわる歴史資料等を収集・保存すると共に展示・公開しています。この博物館では武具・絵画・工芸品・古文書など「しおがまさま」の悠久の歴史とその御神徳を物語る貴重な文化財を目にすることができます。
博物館の展示内容は多岐にわたり、国指定重要文化財を含む宝物を中心に、鹽竈神社にかかわる歴史資的料を展示しています。特に興味深いのは2Fは「塩」について学ぶことが出来る展示室があり、本物の巨大な岩塩の塊が飾られているのが印象的でしたという塩に関する展示で、神社の由来となった製塩技術について詳しく学ぶことができます。
また、祭礼で使用される神輿も重要な文化財の一つです。鹽竈神社の黒漆塗りの神輿は280年以上前に造られました。この神輿の重さは約1トンにもなりますが、祭りの際にはわずか16人の男たちに担がれて市街へと続く202段の石段を下ります。一方、50年ほど前に造られた比較的新しい志波彦神社の神輿は鮮やかな朱色ですとなっており、対照的な美しさを持っています。
参拝・拝観案内

志波彦神社・鹽竈神社への参拝は、神聖な場所への敬意を持って行うことが大切です。両神社は同一境内に鎮座していますが、それぞれ独立した神社として適切な参拝を心がけましょう。境内は自由に参拝できますが、神社の開閉門時間や参拝マナーを守って訪れることが重要です。
参拝作法とマナー
神社への参拝は、まず表参道の石鳥居をくぐることから始まります。鳥居をくぐる際は軽く一礼し、参道の中央は神様の通り道とされているため、左右どちらかに寄って歩くのが作法です。202段の石段を上る際は、一段一段を大切に踏みしめながら心を整えて上りましょう。
手水舎での清めも重要な作法の一つです。右手で柄杓を持って左手を清め、次に左手で柄杓を持って右手を清めます。再び右手で柄杓を持ち、左手のひらに水を受けて口をすすぎ、最後に柄杓を立てて柄の部分を清めます。この一連の動作を一杯の水で行うのが正式な作法です。
参拝の際は、まず軽く会釈してから賽銭を静かに入れ、鈴がある場合は鳴らします。その後、二拝二拍手一拝の作法で参拝します。二回深くお辞儀をし、胸の前で二回拍手を打ち、最後に一回深くお辞儀をして参拝を終えます。願い事がある場合は、拍手の後、感謝の気持ちと共に心の中で唱えましょう。
志波彦神社と鹽竈神社は別々の神社のため、それぞれで参拝することが推奨されます。まず鹽竈神社の別宮、左宮、右宮の順で参拝し、その後志波彦神社に参拝するのが一般的な順序とされています。
年中行事・季節のイベント
志波彦神社・鹽竈神社では年間を通じて多彩な祭礼や行事が行われており、それぞれに深い意味と歴史があります。春から夏にかけては特に盛大な祭りが続き、多くの参拝者や観光客で賑わいます。
3月に行われる「帆手祭(ほてまつり)」は重さ250貫(約1t)の神輿を若者16人が担ぎ、鹽竈神社の参道・表坂を一気に下り、さらに市内を勢いよく御神幸する勇壮な祭りです。この祭りは約300年前、火伏祭として町内の厄除けと繁栄を祈願して始まり、神輿洗いの神事とも呼ばれ、港町塩竈で行われることにちなんで、帆手祭と呼ぶようになりましたという歴史があります。
4月の「花祭」は桜の満開時期に合わせて開催され、安永年間、水害干天のため作物が実らず、氏子が鹽竈神社に祈願したところ、数年を経て気候も回復し作柄が良くなったことから、感謝の意を込めて、氏子祭として神輿が町内を御神幸したのが始まりです。境内の桜が最も美しい時期に行われるこの祭りは、春の訪れを祝う華やかな行事として親しまれています。
夏の最大の行事である「塩竈みなと祭」は、7月に行われる「塩竈みなと祭」は三大船祭に数えられ、前夜祭の花火大会や当日のパレードなど盛大な祭りになっています。海の日の本祭では、陸奥国一之宮・志波彦神社鹽竈神社の御神輿を「御座船(日本唯一の祭り専用船)龍鳳丸・鳳凰丸」に乗せ、吹き流しやのぼりをなびかせた約100隻の供奉船を伴い、松島湾内を5時間にわたって巡幸します。この海上渡御は全国でも珍しく、平成26年に「ふるさとイベント大賞」において最高賞の「内閣総理大臣賞」を受賞するほどの価値ある祭礼です。
秋の収穫感謝祭「初穂曳(はつほひき)」は20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮(しきねんせんぐう)で、神社造営の御用材を運ぶ「御木曳(おきひ)き」にならい、鹽竈神社式年遷宮で御木曳きを行って市内を練り歩いたのが始まりで、11月23日に行われる収穫祭「初穂曳(はつほひき)」には、本殿の前の広場が豊穣と大漁に感謝して捧げられた米俵や巨大な魚、野菜で埋め尽くされます。
2月上旬の節分祭では両神社は春の訪れを告げる盛大な節分祭を開催し、邪気を祓うとされる豆まきを行います。また、夜には若者たちによる「裸参り」が行われますという勇壮な神事も執り行われます。
特別な神事として、製塩法を伝えたとされる鹽土老翁神(しおつちおぢのかみ)を祀る、鹽竈神社の末社・御釜神社で行われる古代製塩の神事である藻塩焼神事があり、7月4日に、花渕浜でホンダワラ(海藻)を刈り取る神事が行われ、5日に神釜の水替神事、6日に古式にのっとり藻塩焼神事と御釜神社例祭が斎行されます。県無形民俗文化財指定という貴重な文化財でもあります。
御朱印・お守り情報
志波彦神社・鹽竈神社では、両神社それぞれの御朱印をいただくことができます。御朱印は神社との縁を記す大切なものですので、御朱印帳を持参して丁寧にお願いしましょう。受付時間は神社の開門時間に準じており、特別な祭礼日などは受付時間が変更される場合があるため、事前に確認することをお勧めします。
お守りについては、それぞれの神社の御神徳に応じた多種多様なものが用意されています。鹽竈神社では航海安全や安産祈願のお守り、志波彦神社では農業守護や事業繁栄のお守りなどが人気です。また、両神社共通のお守りとして、開運招福や家内安全のお守りも授与されています。
特に人気が高いのは塩竈桜をモチーフにしたお守りで、桜の美しさと神社の御神徳が込められた品として多くの参拝者に愛されています。お守りは一年間身につけて、翌年の初詣の際に感謝を込めて返納し、新しいお守りを受けるのが一般的な習慣です。
アクセス・利用情報

志波彦神社・鹽竈神社は宮城県塩竈市の中心部に位置し、仙台市からも電車で約30分という便利な立地にあります。公共交通機関を利用した参拝が推奨されており、特に祭礼日や初詣期間中は混雑が予想されるため、時間に余裕を持った計画を立てることが大切です。
交通アクセス
最寄り駅はJR仙石線の本塩釜駅で、JR仙石線 本塩釜駅より ・表参道(表坂)の石鳥居まで徒歩約15分・東参道(裏坂)の石鳥居まで徒歩7分・社務所前まで徒歩で約15分、タクシーで5分となっています。表参道は歴史ある石段を上る正式な参拝ルートですが、202段の石段があるため、足腰に不安がある方は東参道(裏坂)の利用や、タクシーでの境内まで直行も可能です。
仙台駅からのアクセスは、JR仙石線で約25分、本塩釜駅下車となります。仙台市内からは頻繁に電車が運行されているため、日帰り参拝にも適しています。また、初詣時には、仙石線・東北本線とも深夜から早朝にかけて臨時列車が運行されるため、年末年始の参拝も便利です。
自動車でのアクセスの場合、三陸自動車道利府塩釜インターチェンジから約10分、仙台市内からは国道45号線を利用して約40分程度です。カーナビゲーションを使用する際は「志波彦神社・鹽竈神社」または住所「宮城県塩竈市一森山1-1」で設定してください。
拝観時間・料金・駐車場情報
神社の開閉門時間は季節によって異なり、【志波彦神社】 4月~7月 午前5時~午後5時 8月 午前5時~午後4時30分 9月~10月 午前5時~午後5時 11月 午前5時30分~午後4時30分 12月 午前6時~午後4時 1月 午前6時~午後5時 2月 午前6時~午後4時30分 3月 午前5時30分~午後5時、【鹽竈神社】 3月~10月 午前5時~午後6時まで 11月~2月 午前5時~午後5時までとなっています。
境内への参拝は無料ですが、鹽竈神社博物館は入館有料(令和5年現在、博物館屋上の展望台は閉鎖中につき、立入不可)となっています。博物館の入館料や開館時間については、訪問前に公式サイトで最新情報を確認することをお勧めします。
駐車場については、境内の東側から北側にかけて参拝者専用の無料駐車場が 4か所(第1・第2・第3・バス)があります。300台収容となっており、普通車だけでなくバスでの団体参拝にも対応しています。ただし、初詣期間や主要な祭礼日には駐車場が満車になる可能性が高いため、公共交通機関の利用を強く推奨します。
特別な配慮として、鹽竈神社祈祷者待合室にベビーケアルーム(授乳室)を東北の神社で初導入。 腰かけのある完全個室なので、お気軽に授乳室やおむつ替えとしてご利用いただけますという施設があり、小さなお子様連れの参拝者にも配慮した環境が整備されています。
<住所> 〒985-8510 宮城県塩竈市一森山1-1
参照サイト
・志波彦神社・鹽竈神社 公式サイト:http://www.shiogamajinja.jp/