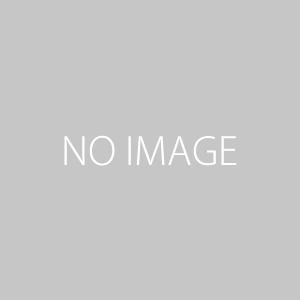宇都宮二荒山神社|下野国一宮の歴史と見どころ、参拝情報を完全ガイド
宇都宮市の中心部、明神山と呼ばれる標高135メートルの小高い丘に鎮座する宇都宮二荒山神社は、約1600年の歴史を誇る由緒ある神社です。下野国一宮として古くから崇敬され、現在も宇都宮市民から「二荒さん」の愛称で親しまれています。都市の中心にありながら豊かな自然に包まれた境内は、まさに都会のオアシスとして多くの人々に愛され続けています。
宇都宮二荒山神社の概要・基本情報

宇都宮二荒山神社は、栃木県宇都宮市にある神社で、式内社(名神大社)論社、下野国一宮として位置づけられています。現在は神社本庁の別表神社に指定され、その格式の高さを物語っています。正式名称は二荒山神社ですが、日光の二荒山神社との区別のために鎮座地名を冠して「宇都宮二荒山神社」と呼ばれています。
歴史と由来
宇都宮二荒山神社の創建は353年と伝わり、その歴史は1600年を超えることになります。第10代崇神天皇の皇子、豊城入彦命が東国を治めたことを起源とし、その後の豊城入彦命の孫、奈良別王によって祀られたのが始まりとされています。
興味深いことに、宇都宮の地名も、ここが神社の格付けで下野国一宮であることから、「一宮(いちのみや)」が転訛して宇都宮になったという説があります。このことからも、神社がこの地域の発展にいかに深く関わってきたかがわかります。
平安時代には下野国一の宮と呼ばれるほど、この地域で重要な神社となり、源頼義や源頼朝、徳川家康らの歴史上の偉人たちも、この神社で戦勝祈願をしたと伝えられています。しかし、神社は幾度もの火災に見舞われ、戊辰戦争においても旧幕府軍と新政府軍がこの境内で戦い、社殿が焼失しました。現在の社殿は戊辰戦争による焼失後の明治10年(1877年)に再建されたものです。
祭神とご利益
宇都宮二荒山神社の祭神は、東国を鎮めたとする豊城入彦命です。豊城入彦命は崇神天皇の皇子で、東国開拓の祖神として崇められています。郷土の祖神・総氏神さまとして崇敬され、そのご神徳は福徳開運を招き、生活に限りない御加護、恩恵をもたらすといわれています。
特に開運招福、商売繁盛、家内安全、厄除けなどのご利益があるとされ、地域の人々の生活に密着した信仰を集めています。また、境内には本社以外にも十二の末社が祀ってあり、安産など様々なご利益を求める参拝者が訪れます。
宇都宮二荒山神社の見どころ・特徴

宇都宮二荒山神社の最大の特徴は、その圧倒的な存在感です。大通りに面した堂々たる大鳥居と、約100段の石段が続く参道は、威厳ある雰囲気を醸し出しています。
建造物・構造の魅力
本殿や拝殿は栃木県の有形文化財に指定されていて、趣のある雰囲気も見どころです。明治時代に再建された社殿は、伝統的な神社建築の美しさを現代に伝える貴重な建造物となっています。
神社の構造も特徴的で、市街地の中心部にありながら明神山の山頂という立地を活かした配置となっています。石段を登りきった境内からは宇都宮市街を一望でき、神聖な空間と日常の世界を結ぶ特別な場所となっています。
境内には、初辰稲荷神社や菅原神社、水神社など、さまざまなご利益を持つ神社が併設されています。これらの摂末社それぞれに特色があり、参拝者の多様な願いに応える場となっています。
自然・景観の美しさ
境内には美しい緑が広がり、宇都宮市民はもちろん、観光客の心も和ます「都会のオアシス」として親しまれています。境内はイチョウや桜、もみじなどが茂り、街の中心部とは思えない豊かな自然に包まれています。
春には桜、秋には紅葉と四季折々の表情を見せる風景も魅力の一つです。特に桜の季節には多くの花見客が訪れ、神聖な空間でありながら市民の憩いの場としても機能しています。
文化財・重要な所蔵品
社宝に国指定重要美術品の三十八間星兜と鉄製狛犬があります。これらの貴重な文化財は、神社の長い歴史と文化的価値を物語る重要な資料となっています。
また、現代的な特色として、宇都宮を代表するご当地グルメである「餃子」にちなんだ「餃子おみくじ」があり、参拝客の人気を集めています。これは宇都宮という地域性を活かした独自の取り組みとして注目されています。
参拝・拝観案内

宇都宮二荒山神社は参拝自由の神社で、境内への立ち入りに特別な制限はありません。ただし、神聖な場所としての敬意を持って参拝することが大切です。
参拝作法とマナー
宇都宮二荒山神社の参拝作法は、一般的な神社と同様の手順で行います。まず大鳥居をくぐる際には一礼し、参道では中央を避けて歩きます。手水舎で心身を清めた後、拝殿前で「二礼二拍手一礼」の作法で参拝します。
特に注意すべき点として、約100段の石段があることから、足元に気をつけて安全に参拝することが重要です。また、境内は市民の憩いの場でもあるため、静粛を保ち、他の参拝者への配慮も心がけましょう。
写真撮影については、境内での撮影は一般的に可能ですが、建物内部や祈祷中の撮影は控えるのがマナーです。SNSなどへの投稿の際も、神聖な場所であることを念頭に置いた節度ある内容を心がけることが大切です。
年中行事・季節のイベント
4月には花会祭、6月は大祓式、7月は須賀神社天王祭、10月は菊水祭など、年間を通して賑わいます。これらの祭事は地域の伝統文化を継承する重要な行事として、多くの市民や観光客が参加します。
中でも7月の須賀神社天王祭は、境内にある須賀神社の例祭として古くから続く伝統行事です。また、正月の初詣期間や七五三の季節には特に多くの参拝者で賑わい、宇都宮市民の生活に深く根ざした神社であることがうかがえます。
近年では、神楽殿でのミュージシャンによる音楽イベントや、鳥居のある広場でのスポーツイベントなど、伝統と現代文化を融合させた新しい取り組みも行われており、幅広い世代に親しまれる工夫がなされています。
御朱印・お守り情報
宇都宮二荒山神社では、御朱印の授与を行っています。社務所の受付時間内であれば、通常の御朱印のほか、季節限定の特別な御朱印も授与される場合があります。夏季には「夏詣」御朱印の授与も始まっており、四季に応じた特色ある御朱印を受けることができます。
お守りについては、一般的な交通安全、学業成就、健康祈願などの各種お守りを授与しています。特に宇都宮らしい特色として「餃子おみくじ」があり、1回300円で箸を使ってつまむユニークな形式のおみくじが人気を集めています。
また、境内の摂末社それぞれにも特色あるお守りやご利益があるため、自分の願いに応じた参拝とお守りの授与を受けることができます。詳細な授与品や料金については、参拝時に社務所で確認することをおすすめします。
アクセス・利用情報

宇都宮二荒山神社は宇都宮市の中心部に位置しているため、公共交通機関、自動車ともにアクセス良好な立地にあります。
交通アクセス
公共交通機関を利用する場合、最寄り駅はJR宇都宮駅と東武宇都宮駅になります。JR宇都宮駅からバスで約5分、JR宇都宮駅西口バスターミナルより市内バス乗車、「馬場町(二荒山神社前)」下車してすぐです。東武宇都宮駅からは徒歩10分の距離にあり、歩いてアクセスすることも可能です。
自動車でのアクセスの場合、宇都宮ICから約20分、東北自動車道鹿沼ICから車で20分程度の所要時間となります。高速道路からのアクセスも良好で、県外からの参拝者にも便利な立地です。
市内中心部に位置していることから、宇都宮観光の拠点としても最適で、他の観光スポットと合わせて巡ることができます。
<住所> 〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り1丁目1−1
拝観時間・料金・駐車場情報
営業時間は6:00~18:00(社務所9:00~16:00)で、定休日は無休となっています。境内への参拝は無料で、特別な拝観料などは必要ありません。ただし、御朱印やお守りなどの授与品については別途料金がかかります。
駐車場については、300台収容可能な有料駐車場があり、料金は60分300円となっています。祈祷を受ける場合は2時間無料で利用できます。駐車場は神社の西側、参道入口付近に位置しており、表参道から参拝したい方は、駐車してから移動が必要で、駐車場から表参道までは徒歩約6分程度です。
参拝時間に制限はありませんが、夜間の参拝については安全面を考慮し、明るい時間帯での参拝をおすすめします。また、お祭りや特別な行事の際には駐車場が混雑する場合があるため、公共交通機関の利用を検討することをお勧めします。
参照サイト
・宇都宮二荒山神社ホームページ:http://futaarayamajinja.jp/