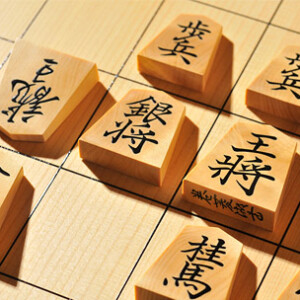加賀てまりとは?その魅力と歴史、特徴など詳しく解説
色とりどりの絹糸をひと針ひと針かがって作り上げる加賀てまり。振ると優しく響く鈴の音と、雅やかな花模様や幾何学模様が美しいこの工芸品は、江戸時代から金沢の人々に愛され続け、幸せを願う縁起物として今もなお大切に受け継がれています。
加賀てまりとは
加賀てまりは、石川県金沢市で作られる伝統的な手まりで、ひと針ひと針、色糸をかがって作られる色鮮やかな花模様や幾何学模様が美しい工芸品です。つややかな絹糸をかがって、雅な模様を描きだすその技法は、長年にわたって受け継がれてきた和の伝統技術の集大成といえます。
加賀てまりの最大の特徴は、中に鈴が入っており、振ると可愛らしい音が鳴ることです。音が良く鳴ると持っている方の運も良くなると言われているそうで、縁起の良い贈り物として広く親しまれています。
てまりは、古くから子供たちの遊びの玩具として親しまれていました。日本全国に様々な地域の手まりが存在しており、南部姫鞠(青森県八戸市)、本荘ごてんまり(秋田県由利本荘市)、御殿まり(山形県鶴岡市)、栃尾手まり(新潟県長岡市栃尾)、野州てんまり(栃木県宇都宮市)、須坂の手まり(長野県須坂市)、松本てまり(長野県松本市)、小松の口かがり糸まり(静岡県浜松市)、紀州てまり(和歌山県和歌山市・田辺市など)、松山姫てまり(愛媛県松山市)、博多てまり(福岡県福岡市)、肥後てまり(熊本県熊本市)、琉球手まりなどがあります。
その中でも加賀てまりは、金沢という加賀百万石の文化的土壌の中で独自の発展を遂げ、装飾品として、お部屋に飾られることも多くなり、身近に愉しめる金沢の大切な工芸品のひとつとなっています。
金沢では娘が嫁ぐ際に手縫いのまりを魔除けとして持たせる習慣があり、縁起の良い贈り物として広く親しまれています。現在でも娘が嫁ぐときに、幸せを願って持たせるという習慣が続いており、そのため加賀てまりは単なる工芸品を超えて、家族の愛情と幸せへの願いが込められた特別な存在となっています。
加賀てまりが生まれた背景
加賀てまりの金沢への伝来は江戸時代で、徳川家から加賀藩主に嫁いだ珠姫様がお持ちになったことが始まりだと伝えられています。
珠姫は慶長4年(1599年)に徳川二代将軍秀忠の次女として生まれました。母のお江は織田信長の妹、お市の方の娘で、豊臣家とも親戚にあったことから、珠姫は織田家、豊臣家、徳川家という戦国最強の家系につながる姫君でした。
慶長6年(1601年)、いまだ天下の情勢が不透明ななか、珠姫が徳川家と前田家の架け橋となるべく金沢城に輿入れしたのはわずか3歳のときでした。14歳で5歳年上の利常公と結婚し、三男五女に恵まれました。ふたりはたいへん仲睦まじく、珠姫が実父の将軍に「江戸に滞在中の夫を早く国元に帰してほしい」と手紙を書いたというほほえましいエピソードも残されています。
珠姫は徳川家康の愛娘として、また前田家の正室として、江戸時代初期の政治的に不安定な時期に徳川家と前田家の友好・主従関係の証として重要な役割を果たしました。彼女の存在により、加賀百万石の平和と繁栄が保たれたといっても過言ではありません。
江戸時代に加賀藩主に徳川家から嫁いだ珠姫様が、嫁入り道具の一つとして持参したことにより、金沢に広まったと言われています。それ以来金沢では、女の子が嫁ぐ時には、幸せを願い持たせる習慣が定着しました。
このように加賀てまりは、単なる玩具や装飾品としてだけでなく、政治的な意味合いも持った特別な工芸品として金沢の地に根付いたのです。珠姫の存在とともに加賀てまりも金沢の文化の一部となり、現在まで大切に受け継がれています。
加賀てまりの歴史
加賀てまりの歴史は、江戸時代初期の1601年に珠姫が金沢に輿入れしたときに始まります。わずか3歳で江戸から遠く離れた金沢へきた徳川家康の愛娘である珠姫は、徳川家と前田家の架け橋として重要な役割を担いました。
珠姫が持参した手まりは、当初は子供の玩具として用いられていましたが、その美しさと縁起の良さから次第に金沢の人々の間に広まっていきました。加賀百万石という豊かな文化的土壌の中で、手まりは単なる玩具を超えて芸術的な工芸品へと発展していきました。
江戸時代を通じて、加賀てまりは金沢の女性たちの間で大切に作り続けられました。母から娘へ、祖母から孫へと技術が受け継がれ、その過程で様々な模様や技法が生み出されていきました。特に娘が嫁ぐ際に幸せを願って持たせるという習慣が定着し、加賀てまりは単なる工芸品を超えて、家族の愛情と幸せへの願いが込められた特別な存在となりました。
しかし幸せな時間は突然終わりを告げ、元和8年(1622年)、珠姫は24歳の若さで亡くなってしまいます。その死を悼み、夫である利常が妻の菩提寺として創建したのが天徳院です。天徳院は曹洞宗のお寺で、珠姫の戒名「天徳院殿乾運淳貞大禅定尼」から名づけられました。
珠姫の死後も、加賀てまりは金沢の文化として継承され続けました。加賀百万石の繁栄とともに、手まりの技術も洗練され、より美しく精巧な作品が作られるようになりました。
明治時代以降も、加賀てまりの伝統は途絶えることなく受け継がれました。近代化の波の中でも、金沢の女性たちは手まり作りの技術を大切に守り続け、現代まで伝統を継承してきました。
現在では、加賀てまりは石川県の代表的な工芸品の一つとして認知され、国内外から高い評価を受けています。伝統的な技法を守りながらも、現代的なデザインや用途にも対応し、インテリアとしても素敵な存在として多くの人々に愛されています。
また、珠姫の菩提寺である天徳院では、からくり人形「珠姫・天徳院物語」が上演され、珠姫の生涯と加賀てまりの歴史を多くの人々に伝えています。このように加賀てまりは、単なる工芸品を超えて、金沢の歴史と文化を物語る貴重な文化遺産として現在も大切に保存・継承されています。
加賀てまりの特徴・魅力
加賀てまりの最大の魅力は、つややかな絹糸をかがって描き出される雅やかな模様にあります。ひと針ひと針、色糸をかがって作られる色鮮やかな花模様や幾何学模様は、見る者の心を奪う美しさです。伝統的な模様をモダンにアレンジしたデザインは情感たっぷりで、インテリアとしても素敵な存在となっています。
折々の風物詩を映したデザインは、四季の移ろいや日本の美に思いを馳せながらひと針ひと針作り上げられます。この丁寧な手仕事により生み出される美しく縁起のよい加賀てまりは、こころ豊かな時間を提供してくれます。
加賀てまりの特徴的な要素の一つが、中に入っている鈴です。振ると柔らかく可愛らしい音が鳴るのが特徴で、音が良く鳴ると持っている人の運も良くなると言われています。この音は控えめで上品な響きを持ち、音を鳴らすとお金持ちになれるという言い伝えもあるそうです。
色彩の美しさも加賀てまりの大きな魅力です。色により分類される様々な色合いがあり、どれも素朴かつ上品な味わいがあります。金沢という加賀百万石の文化的土壌で育まれた美意識が、色使いの洗練さにも表れています。
加賀てまりは実用性と装飾性を兼ね備えた工芸品でもあります。古くは子供の玩具として用いられていましたが、現在では装飾品として、お部屋に飾られることも多くなり、身近に愉しめる金沢の大切な工芸品のひとつとなっています。
縁起物としての意味合いも加賀てまりの重要な特徴です。金沢では娘が嫁ぐ際に手縫いのまりを魔除けとして持たせる習慣があり、縁起の良い贈り物として広く親しまれています。良縁、家庭円満、財運といった願いが込められ、特別な人生の節目に贈られる意味深い存在です。
また、加賀てまりには手作りならではの温かみがあります。一針一針手作りで制作されるため、同じ模様でも微妙な違いがあり、それぞれが世界に一つだけの特別な作品となります。この手仕事の温もりが、現代の機械化された社会において特に価値のあるものとなっています。
加賀てまりは、受け継がれてきた和の技法を土台作りから仕上げまで存分に堪能できる工芸品でもあります。伝統的な技術と現代的な感性が融合することで、時代を超えて愛され続ける美しい作品が生み出されています。
加賀てまりの制作の流れ
加賀てまりの制作は、まず土台となる球体作りから始まります。この土台作りが加賀てまりの基礎となる重要な工程で、しっかりとした球形を作ることが美しい仕上がりの鍵となります。
土台ができたら、地割りという作業を行います。まずは北極を決め、地割りテープとスケールを使って南極と赤道を設定します。てまりを地球に見立てたこの位置決めは、模様を正確に配置するための重要な準備作業です。
赤道テープとスケールを使って、まち針を等間隔に刺し直します。この下準備により、後の模様付けが正確に行えるようになります。ラメ糸でまち針に沿って、縦と横に線を付け、便利な型紙を使って、かがる段数の目印をつけていきます。
いよいよ球体に刺繍を施す段階に入ります。デザインによって、かがりのスタート位置は変わりますが、多くの場合は赤道まわりからスタートします。ここでは巻くだけの作業ですが、球の大きさに沿わせて引きすぎずゆるすぎず、やさしく糸を巻いていくことが重要です。
かがり作業では、つややかな絹糸を使って模様を描いていきます。この工程が加賀てまりの美しさを決定する最も重要な部分で、職人の技術と感性が問われます。花模様や幾何学模様など、様々なデザインをひと針ひと針丁寧にかがっていきます。
模様をかがる際には、色の配置や糸の張り具合に細心の注意を払います。同じ模様でも、色の組み合わせや糸の密度によって全く異なる印象の作品に仕上がります。この微妙な調整が、加賀てまりの芸術性を高める要素となっています。
制作過程では、常に全体のバランスを確認しながら作業を進めます。球体という立体的な形状に模様を施すため、平面とは異なる技術が必要になります。どの角度から見ても美しく見えるよう、立体的な美しさを意識した制作が求められます。
最終的な仕上げでは、糸の始末や細部の調整を行います。糸端の処理や模様の微調整など、細かな作業が作品の完成度を左右します。この段階で、中に入れる鈴の音の確認も行い、美しい音が出るよう調整します。
完成した加賀てまりは、一つ一つが手作りの温もりを持った世界に一つだけの作品となります。同じ模様を作っても、作り手の個性や微妙な手の動きの違いにより、それぞれ異なる表情を持つ作品に仕上がります。
現在では、てまり作家の指導による加賀てまりの制作体験も行われており、多くの人が伝統的な技法を学ぶ機会が提供されています。約2時間の体験では完成まではいきませんが、続きは持ち帰って完成させることができ、手作りの喜びを味わうことができます。
まとめ
加賀てまりは、江戸時代初期に徳川秀忠の次女である珠姫が加賀藩に嫁いだ際に金沢にもたらされた、400年以上の歴史を持つ伝統工芸品です。つややかな絹糸をひと針ひと針かがって作り上げる美しい花模様や幾何学模様と、振ると響く優しい鈴の音が特徴的な、まさに金沢らしい雅やかな工芸品といえます。
加賀百万石の文化的土壌の中で育まれた加賀てまりは、単なる子供の玩具から芸術的な工芸品へと発展し、現在では装飾品としても多くの人に愛されています。特に金沢では娘が嫁ぐ際に幸せを願って持たせる習慣が続いており、良縁、家庭円満、財運を願う縁起物としての意味も持っています。
一針一針手作りで制作される加賀てまりは、同じ模様でも微妙な違いがあり、それぞれが世界に一つだけの特別な作品となります。この手仕事の温もりと、伝統的な技法を現代に伝える職人たちの努力により、加賀てまりは時代を超えて愛され続ける貴重な文化遺産として現在も大切に継承されています。
四季の移ろいや日本の美に思いを馳せながら作られる加賀てまりは、見る者の心に豊かな時間をもたらし、金沢の歴史と文化を物語る美しい工芸品として、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。